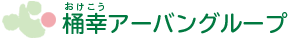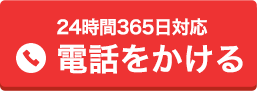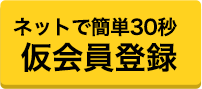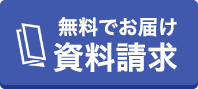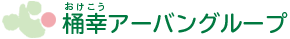1.四十九日法要とは?
2.四十九日法要の方法は?
3.まとめ
1.四十九日法要とは?
49日法要とは、故人様が亡くなってから49日後に行う法要のことです。
仏教では亡くなってから7日毎に7回の審判を受け、極楽浄土へ行けるかどうかの判決が下されると考えられています。そのため、残されたご家族は7日毎に法要を行うことで故人様の冥福を祈ります。
また浄土真宗では亡くなった人はすぐに極楽浄土へ行けるという教えのため、極楽浄土へ行けるように祈るのではなく、故人様を偲ぶために49日法要を行うとされています。
日数の数え方は、仏教では一般的には亡くなった日を1日目と数えるため、正確には亡くなった日から48日後が49日になります。
一部の地域では、亡くなった前日を1日目と数えることもありますので確認が必要です。
2.四十九日法要の方法は?
49日法要を行う場所としては、以下が挙げられます。
- お寺
法要と共に本位牌や仏壇等の開眼法要を行う場合も多いため、一緒に行うことがで
きます。また、法要に必要な道具や設備も揃っているため準備の負担を減らすこと
ができます。
- 自宅
小規模の法要を行う場合に適しています。慣れている場所で法要を行うことがで
き、費用を抑えることができます。
一方で、法要に必要な祭壇や供物等を自分で用意しなければならなかったり、駐車
場の確保や終了後の片付け等に苦労される方もいらっしゃるようです。
- 葬儀社の式場
専門のスタッフが常駐しており、設備等も揃っているため、事前の準備や当日の法要の進行等の負担を減らすことができます。また、参列者が多い場合にも対応することができます。
また、法要の内容については、どの場所で法要を行っても法要の基本的な流れはあまり変化はなく、下記のようになります。
1.参列者着席
2.お寺様着席
3.読経
4.焼香
5.法話
6.喪主挨拶
7.納骨・お墓参り
8.会食
9.締めの挨拶・解散
最近では、永代供養のため納骨を行わなかったり、お身内のみで行うために会食をしなかったりする場合も増えてきています。
49日法要を行う前には、あらかじめ、案内状の作成やふるまう料理や土産の手配・本位牌の用意等をしておく必要があります。
お寺様との事前の打ち合わせも必要になるため、お寺様の都合を確認し、早めに予定を確認しておきましょう。
また、法要後そのまま納骨される場合も多くあるため、必要に応じてお墓の掃除や用意をしておくとよいでしょう。
3.まとめ
49日法要は、故人様が極楽浄土へ行けることを祈って行う大切な法要です。
また49日は、法要を行って故人様を供養するだけでなく、『忌明け』という喪に服する期間が終わる日でもあります。
準備しなければいけないことや、用意しなければいけないもの等が多くあるため、ご家族やお寺様と相談し、できるだけ時間に余裕をもって準備を進めるようにしましょう。
桶幸アーバングループでは、49日法要のお手伝いを随時承っております。ご不明点やご質問がございましたら、いつでもお問い合わせくださいませ。