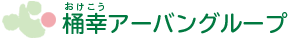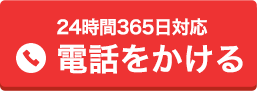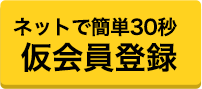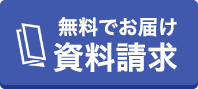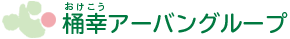1.併修・合斎とは?
2.併修・合斎を行うメリットは?
3.併修・合斎を行う時の注意点は?
4.まとめ
1.併修・合斎とは?
併修・合斎とは、同じ年に2つ以上の法要が重なった場合にそれらをまとめて同時に行うことを指します。
併修・合斎を行うことができる法要は、七回忌以降の法要といわれています。三回忌までの法要はまとめて行わず、個別に行うことが望ましいでしょう。
お寺様や地域によってはまとめて行うことができる法要の範囲が異なることもありますので、事前に確認しておく必要があります。
2.併修・合斎を行うメリットは?
併修・合斎を行うメリットとして以下のことが挙げられます。
- 身体的・時間的な負担の軽減
複数回に分けて行われるはずの法要をまとめて1回で行うことができれば、法要の為の準備や移動等に必要な身体的・時間的な負担を軽減することができます。
ご遺族の高齢化や遠方のご親戚を招く場合には大きなメリットになるでしょう。
- 金銭面の負担の軽減
複数回行うはずの法要を1つにまとめて行えば、会場代・香典・お料理代・お土産代、場合によっては移動・宿泊費等の金銭面の負担の軽減にもなります。
お布施に関しては、2人分の法要をまとめるから通常の2倍必要というわけではありません。相場としては通常1人分の1.5倍程度と言われてはいますが、お寺様によって異なりますので菩提寺へ確認するようにしましょう。
3.併修・合斎を行う時の注意点は?
併修・合斎を行う時の注意点は以下のようになります。
- 日程の決め方
同じ年に亡くなった方の法要を行う場合は、先に亡くなった方の命日に合わせて法要の日程を決めます。
亡くなった年が違う場合は、亡くなられた年が浅い方の命日に合わせて法要の日程を決める場合と、亡くなった日が早い方に合わせて決める場合とがありますのでお寺様やご家族と相談して決めるようにしましょう。
- 同じ年に行われる法要をまとめる
併修・合斎とは同じ年に行われる法要をまとめて行うことを指します。
基本的には別の年に行われる法要をまとめて行うことはできません。
また、同じ年に行われる法要でも、あまりにも期間が空きすぎている場合はまとめて行うことは避けた方がよいでしょう。
期間が開いている場合や年が異なる法要をまとめたい場合は必ず菩提寺に相談しましょう。
- 事前に説明をしておく
法要をまとめて行う場合は、参加する方に案内状等で事前にまとめて行うことを知らせておきましょう。併修・合斎自体はマナー違反というわけではありませんが、参加する方の中には併修・合斎をあまり良く思わない方もいらっしゃるかもしれません。後々のトラブルを避けるためにも事前の案内はしておきましょう。
また、案内状を作成する際には『誰と誰の法要を行う』かは必ず記載するようにしましょう。
記載の順番は、亡くなられた年が浅い方から順番に書くようにすると良いでしょう。
4.まとめ
近年では高齢化や生活様式の変化・法要に対する考え方の変化等から併修・合斎を行うご家庭が増えてきています。
しかし、まとめて法要を行うからといって故人様を偲ぶ気持ちがおざなりになってしまわないようにしましょう。
また、故人様への思いや法要を行うことについての考え方はそれぞれ異なり、それぞれの法要をそれぞれ個別に行うべきと考える方もいらっしゃいます。併修・合斎を行おうとする場合は、必ず事前に菩提寺様やご親族と相談をして決めるようにしましょう。